墓標

1/70
モンゴルの首都、ウランバートルから東へ、ゴルヒ・テレルジ国立公園へ向かう。
途中、車窓から見えたのは墓地。
丘陵の斜面に、無数の墓標が並ぶ。チンギス・ハーン騎馬像

2/70
しばらく東へ進むと、エレデネ村に入る。
車窓から銀色に輝く、巨大な建造物が見えて来た。
チンギス・ハーン騎馬像だ。チンギス・ハーン騎馬像
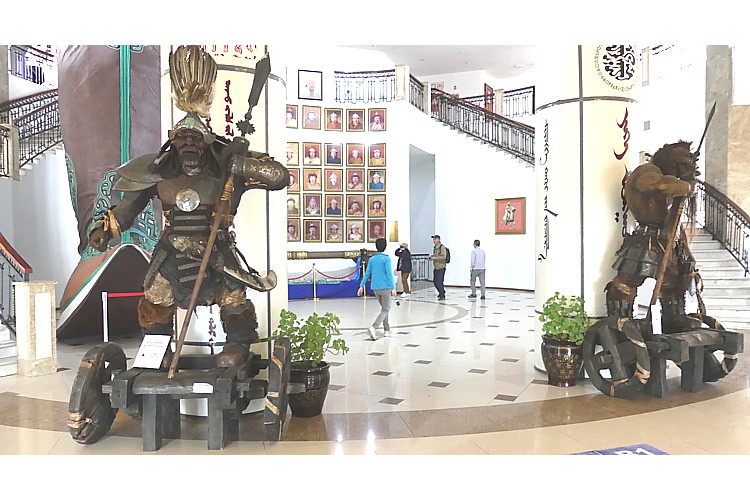
3/70
建物入り口までは緩やかな階段を上り、そこから騎馬像の台座部分の館内へ。
入った先は展示物が置かれる博物館となっている。チンギス・ハーン騎馬像

4/70
モンゴルの遊牧民が暮らす、伝統的な移動式住居のゲル。
同じ物は中国ではパオ、中央アジアではユルタとなる。
ゲルの北西の角は神聖な場所で、仏像を安置する。チンギス・ハーン騎馬像

5/70
階段から見下ろした館内の風景。
巨大な伝統的モンゴル・ブーツや歴代の皇帝、ハーンの肖像画、チンギス・ハーンが手にしていたとされる、黄金の鞭などが展示されている。チンギス・ハーン騎馬像

6/70
館内から、騎馬像のお尻辺りに設置されているエレベーターで上に。
チンギス・ハーンの腹辺りから、馬の首を通ると展望台に出る。
展望台から振り返って、チンギス・ハーン騎馬像の風景。チンギス・ハーン騎馬像

7/70
展望台は高さ30mにあり、そこからはモンゴルの雄大な大平原の絶景が見渡せる。
騎馬像のチンギス・ハーンは、自身が征服した大地を得意げに、誇らしく眺めている様だ。チンギス・ハーン騎馬像

8/70
入り口の門。
モンゴル帝国を築いた、快進撃をした騎馬軍団の像が上に乗っている。
チンギス・ハーン騎馬像が建つこの地は、古くから勝利と繁栄をもたらすとされる黄金の鞭を、チンギス・ハーンが見つけたとされる地。チンギス・ハーン騎馬像

9/70
敷地内には観光用のラクダがおり、乗って記念撮影できる。
またタカもいて、腕に乗せて記念撮影できる。
テーマパーク的なチンギス・ハーン騎馬像。車窓風景

10/70
チンギス・ハーン騎馬像を後に、東へ向かう。
平原ばかりの車窓風景が、岩山の風景へと変わって行く。恐竜の谷

11/70
車窓に恐竜が見えて来た。
ここは恐竜の谷と呼ばれる、恐竜のモニュメントが置かれたテーマパーク。
実際に恐竜の化石が多く発見されるのは、ここでは無く、南のゴビ砂漠。観光牧場へ

12/70
次は観光牧場へ。
連れて来られたのは、清らかな水が流れる、川の岸辺。
さて、どこに牧場があるのかな。観光牧場へ

13/70
しばらく、川の流れを眺めていると、突然ワゴン車が川へ入って行った。
なんだなんだ!と見ていると、続いてジープも水の中へ。
川の対岸の奥に牧場がある様だ。観光牧場へ

14/70
川には橋は架けられておらず、浅瀬を四駆の車で突き切って、向こう岸に渡っていた。
何とも、ワイルドな移動の仕方。観光牧場へ

15/70
河原でヤクに乗っていた地元の人。
高原に生きるヤクは、モンゴルでも貴重な使役動物となっている。
ただこのヤクは、余り人の言う事を聞かなさそうだ。観光牧場へ

16/70
川を渡る車は、水が入らない様にどれも排気マフラーを屋根位の高さに付ける、いわゆるシュノーケル・マフラーを取り付けている。
どれも、結構なポンコツ車なので、ドアの隙間から水が入らないのかな。観光牧場へ

17/70
これから川を渡ります。
大丈夫と判っていても、水浸しにならないか心配。
渡ってからも、デコボコのワインディングロードが続く。観光牧場到着

18/70
デコボコ道で、しこたまシートにお尻を打ち付けながら、観光牧場に到着。
入り口、ゲートの風景。観光牧場

19/70
場内ではいくつかの家畜に触れ合う、アトラクションが用意されている。
ここは乗馬のコーナー。観光牧場

20/70
ここはヤクに触れ合うコーナー。
筆者も乗ってみました。
ヤクはヒマラヤ周辺から天山山脈、チベット高原、モンゴルなど、標高の高い草原や岩場に暮らす、バイソンに近い牛の仲間。観光牧場

21/70
ここは牛車のコーナー。
牛車と言っても屋根も座席も無い、荷車の荷台に絨毯が敷かれているだけの、粗末な乗り物ですが。観光牧場

22/70
牧場にいたワンちゃん。
観光客が多いからか、人に慣れていて、とっても人懐っこい。
とても牧羊犬には成れなさそうだ。観光牧場

23/70
荷車を引くウシ君。
牛車は竹富島や、由布島から西表島へ、浅瀬の海を渡る牛車が良く知られている。
最もどちらも水牛ですが。観光牧場

24/70
筆者も牛車に乗ってみました。
牛車に揺られて、のんびりゆっくり、牧場内を巡る。観光牧場

25/70
乗り心地はお尻が痛くなり、お世辞にも良いとは言えないが、未舗装の林の中を進む、野趣味たっぷりの時間でした。
観光牧場

26/70
最後は四駆で丘の上までドライブ。
森と草原が広がる、壮大な広さの観光牧場の風景。
ここでは冬季、犬ぞりのアトラクションもある。仏像岩

27/70
観光牧場を後に山岳地帯を走る。
途中の岩山に仏像岩、と呼ばれる岩があった。
合掌している仏像に似ている、との事。遊牧民宅訪問

28/70
途中、草原のゲルに暮らす、遊牧の民のお宅を訪問。
ゲルの中に入り、ヤギのチーズ作りを見せてもらいました。遊牧民宅訪問

29/70
外では囲いの中で育てられている子ヤギ、子ヒツジとのふれあい。
女の子が追っかけていました。グローリー・リゾート・モンゴリア

30/70
一日の行程が終わり、宿泊地へ。
ここはグローリー・リゾート・モンゴリア。
岩山の裾野に広がる、広い敷地を持つホテル。グローリー・リゾート・モンゴリア

31/70
このホテルの特徴は、各部屋がゲルの形になった、離れになっているコテージである事。
もちろん、本館には通常の客室もあるのだが、野趣味たっぷりのゲルに泊まるのは最高。モンゴル民族音楽

32/70
夕食時にはモンゴルの民族音楽の調べが催された。
民族楽器、ホーミーでの民謡などを楽しみました。モンゴル民族音楽

33/70
馬頭琴の演奏。
糸巻きの先端が馬の頭の形をしている所から名前が付いた、モンゴルの代表的な民族楽器で、モリンホールとも呼ばれる。
弦や弓も馬のしっぽの毛で作られている。モンゴル民族音楽

34/70
リンベと呼ばれる横笛の演奏。
少し高音の音色は小鳥のさえずりを表現している。
そして驚いたのは、笛の演奏にも関わらず、途中で一切息継ぎをしない事。
これは循環呼吸法と呼ばれる、口の中の息を吐いて演奏しながら、鼻から息を吸い込むと言う、とても理解しがたい演奏です。モンゴル民族音楽

35/70
だみ声や唸った声で歌うハイラフ、これは吟遊詩人の弾き語りが伝承された歌い方。
歌い方にはいくつかあり、他にはオルティンドーやボギノドー、ドーラフなどがある。モンゴル民族音楽

36/70
モンゴル民族音楽の歌い方で、最も有名なのはホーミー。
喉歌と呼ばれ、喉を震わせ低い声と、笛のような高い音を同時に発声する歌唱法の事。
これらモンゴル民族音楽のホーミーや循環呼吸法で演奏するリンベ、馬頭琴演奏はユネスコの無形文化遺産に指定されている。朝日鑑賞

37/70
日の出前、岩山に昇る朝日を見に行きます。
ひんやりと冷たく澄んだ空気を吸いながら、清々しい朝日の鑑賞。朝日鑑賞

38/70
低い位置からの日光に、強いコントラストの風景。
ちなみに、昨晩は人工的な光が少ないモンゴルの平原で、美しい星空も鑑賞しました。
もっとも、カメラやビデオに映る程の光ではありませんでしたが。グローリー・リゾート・モンゴリア

39/70
野趣味満点のゲルでの宿泊を終え、ホテルを出発です。
快晴の朝のグローリー・リゾート・モンゴリアの風景。サブマリン・ロック

40/70
奇岩・珍岩が多いゴルヒ・テレルジ国立公園の山岳地帯を通ります。
この岩はサブマリン・ロック。
中央の突起は潜望鏡があるセイル、艦橋で、左端は船尾の舵がある潜水艦に見える事から。アリヤバル寺院
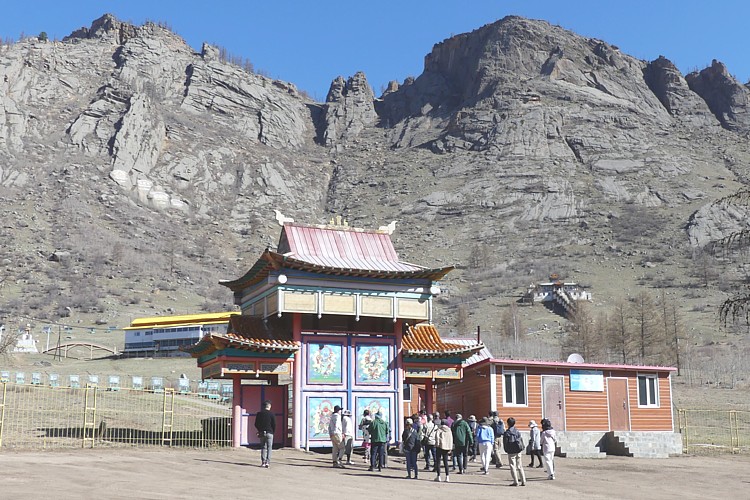
41/70
アリヤバル寺院に到着。
アリヤバル寺院はチベット仏教の寺院で、山岳地帯の岩山の麓に建つ。
境内はとても広く、右中に見えている本堂まで、そこそこ歩きます。アリヤバル寺院
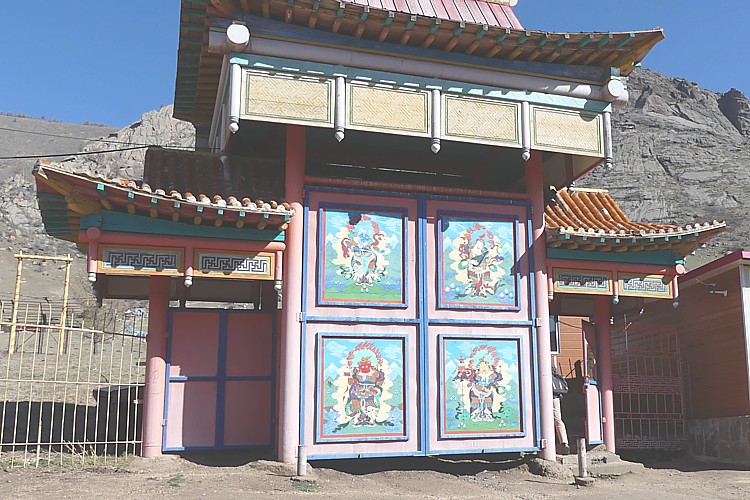
42/70
アリヤバル寺院の山門の風景。
山門には曼荼羅に登場する、チベット仏教の神々の姿が描かれている。
これから門をくぐり、中へ入ります。本堂

43/70
山門あたりから見た本堂の風景。
遠目に眺めると本堂が象の頭、本堂まで上る階段が象の鼻と言う様に、寺院が象の顔に見えると言われる。経文
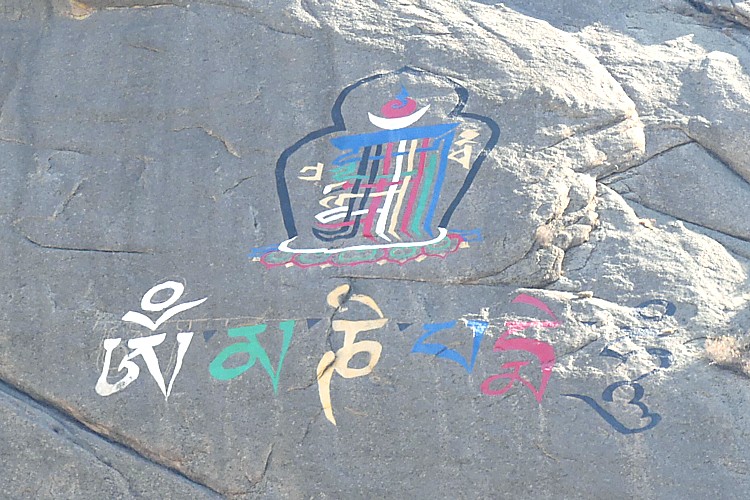
44/70
山門から北へ山すそを上って行く。
東側の岩山の壁に何やら描かれている。
これはチベット文字で書かれた仏教の経文。仏塔

45/70
更に進むと仏塔があり、橋が架けられていた。
特に川が流れている訳では無いのだが。
これは神がいる神域と、我々の俗世とを結ぶ意味での橋。オキナグサ

46/70
春のモンゴル、裾野には可憐な山草が咲いていた。
これはオキナグサ、モンゴルではヤルゴイと呼ばれる春一番を告げる花。
茎や葉に細い綿毛があり、種が入る実も綿毛に包まれ、その姿が老人、翁の頭に見える事から翁草と呼ばれる。お堂

47/70
長い上り坂の参道を北へ進むと、六角形のお堂があった。
参道脇には英語とモンゴル語で書かれた100枚以上のパネルが、道に沿って立っていた。
これらは全て仏教の経典が書かれた板、だとの事。マニ車
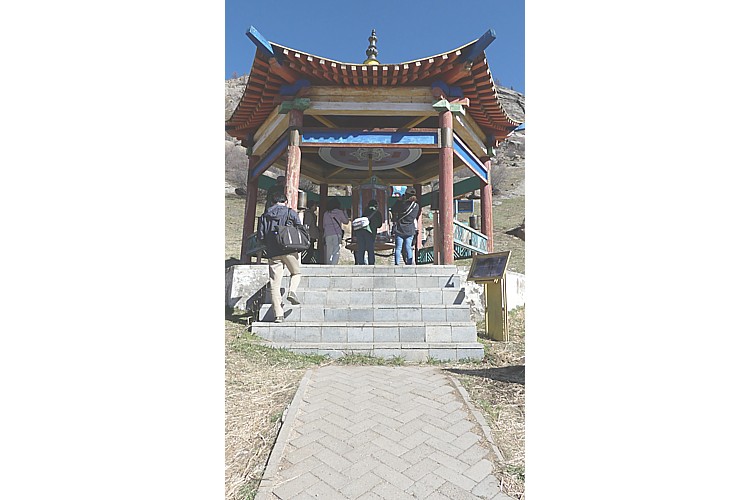
48/70
六角形のお堂の中には、巨大なマニ車が置かれていた。
マニ車は円筒形をしており、手で回せる。
中に経文が入っており、参拝者が回すとお経を唱えた事になり、ご利益がある。亀石

49/70
マニ車のお堂の西側には、亀の形の石が置かれていた。
チベット密教の経典に登場する山亀、あるいは石亀で、甲羅部分は曼荼羅の世界観を表し、石碑を背負う。
亀は長寿を意味し、煩悩への捉われから解放され、仏の知恵を表す。仏壁画

50/70
六角形のお堂から参道を北へ突き当たると、仏壁画のある祭壇があった。
ここから参道は東へと向きを変える。
上り坂はまだまだ続きます。参道

51/70
参道の途中から、上って来たアリヤバル寺院の境内の風景。
周りを岩山で囲まれた、なだらかな草原が広がる。
初夏にでもなれば、一面緑の絨毯になるのだろう。祭壇
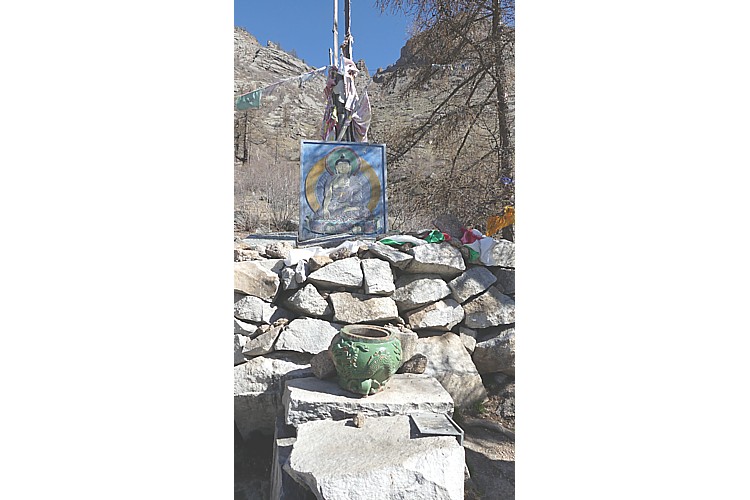
52/70
チベット仏教らしい、石積みの祭壇。
塔の先端には五色の旗、タルチョーが付けられていた。
タルチョーの旗は青、白、赤、緑、黄で、それぞれが世界を構成する天、風、火、水、地を意味する。本堂

53/70
参道の途中からの本堂の風景。
アリヤバル寺院の建物自体は、それ程古くは無い。
旧ソ連の影響を強く受けていた、社会主義国時代のモンゴル人民共和国だった頃、仏教弾圧があり、多くの仏教寺院が取り壊された。吊り橋

54/70
深い谷を渡すかの様に、吊り橋が架けられていた。
何とも頼り無い吊り橋だが、この橋から先は仏の聖なる領域となる、いわゆる結界となっている吊り橋。本堂への石段
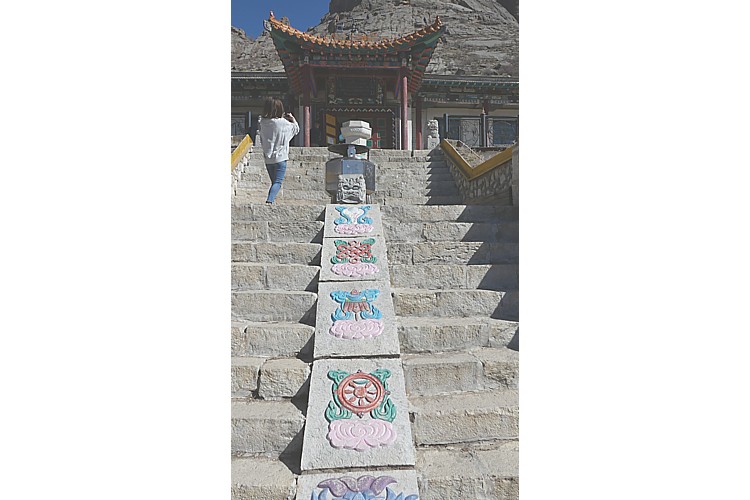
55/70
吊り橋を渡り、ようやく本堂の下までたどり着きました。
さて本堂へ、と見上げると、なんと急勾配の石段が。
石段は108段あった。
精神を浄化するため、煩悩の数だけ上れってか。本堂

56/70
ヘロヘロになりながら、ようやく本堂へ。
堂内へ足を踏み入れた瞬間、ここは仏の世界となる。
神聖な堂内は、鮮やかな極彩色の空間が広がる。本堂

57/70
仏にお祈りを捧げる参拝者。
アリヤバル寺院は瞑想寺院でもある。
元々はチベット仏教僧の修行の寺であり、現在でも参拝者が座禅を組み、瞑想を行う事ができる。奥の院

58/70
本堂から更に上へと、参道は続いている。
先には別のお堂があった。
奥の院、といった所か。
奥の院への参道途中からの、振り返って本堂の風景。奥の院

59/70
奥の院に到着。
早速、お堂の中へ。
とても小さく、狭い堂内だったが、釈迦の生涯を描いたチベット仏教の仏画が飾られていた。
右下に映っているのは、緑色の翡翠の僧侶像。マニ車

60/70
再び本堂まで戻って来ました。
本堂の裏手に回ると、沢山のマニ車が置かれていた。
チベット仏教はラマ教とも言い、化身ラマを尊崇する。
参拝者は一つずつマニ車を回しながら進み、徳を積み、功徳を得る。吊り橋

61/70
本堂から下りる、108段の石段から望む、吊り橋の風景。
木の板を敷いただけの吊り橋、大勢が一斉に渡ると落ちそうなので、譲り合いながら渡ります。菩薩

62/70
吊り橋の手前の参道に置かれていた、涅槃に入る菩薩様。
とても揺れる結界の吊り橋を渡り、筆者の様な俗物は、さっさと俗世へと戻るとしますか。アリヤバル寺院

63/70
アリヤバル寺院は19世紀初頭に、仏教僧侶の修験道の瞑想寺院として、山の麓に建てられた。
社会主義国となったモンゴルでは、旧ソ連の厳しい社会主義路線に反発し、チベット仏教僧たちが指導者となり、暴動を起こす。旧ソ連の最高指導者、スターリンは鎮圧のため、数々の仏教寺院を破壊し、多くの僧侶は捕らえられ、処刑された。
アリヤバル寺院も取り壊されたが、2000年頃から再建が始まり、現在ではモンゴルで最も名高い、チベット仏教寺院となっている。アリヤバル寺院
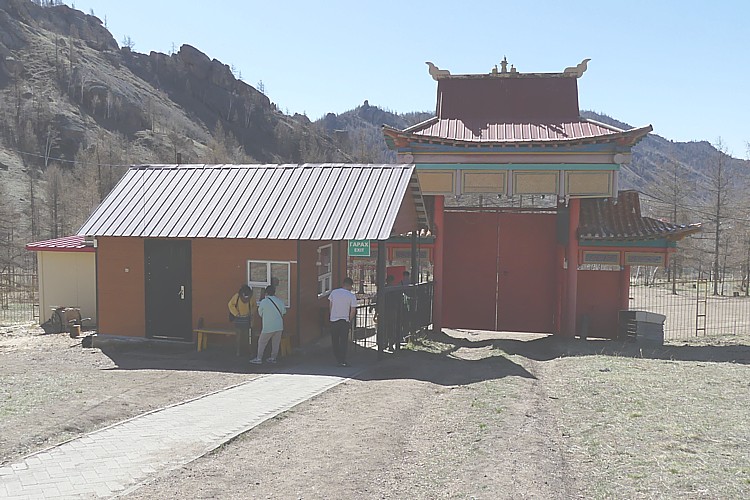
64/70
山門まで戻って来ました。
山門東側に付属する様に、小さなショップが置かれていた。亀石

65/70
ゴルヒ・テレルジ国立公園の観光を終えて、首都ウランバートルへ向かいます。
途中にあった亀石と呼ばれる珍岩。
山岳地帯のゴルヒ・テレルジ国立公園には、何かに似ている、名前が付いた岩がいくつも有る。ビジターセンター

66/70
亀石のビジターセンター。
ゲルの形に建てている。
お土産などのショップもある。亀石
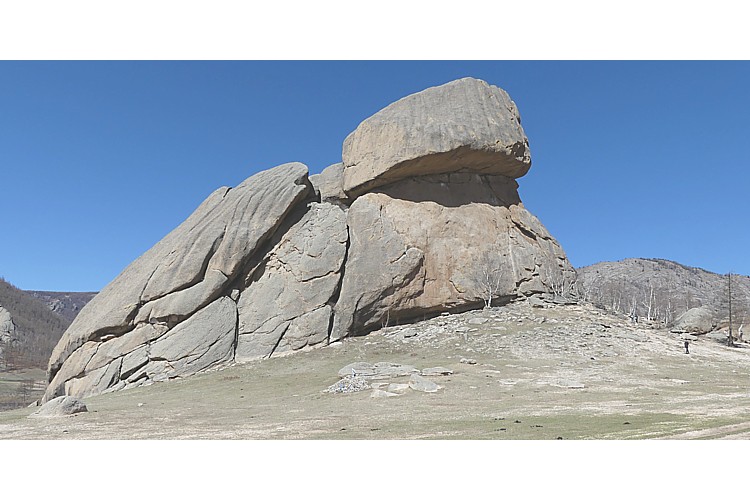
67/70
遠目に見るとカメに見える事からタートル・ロック、亀石と呼ばれている。
ゴルヒ・テレルジ国立公園は広大な面積を持ち、観光用に開発されている部分は僅か。
ほとんどの部分は野生動物が暮らす未開の地で、道も無い。岩山

68/70
亀石の周辺も山岳地帯で、いくつもの険しい岩山がある。
山岳登山やロッククライミングが盛んで、クライマーに人気の岩山も数多くある。タカ

69/70
ビジターセンター近くで、観光客向けにタカが待っていた。
中々精悍な顔つきのタカ君。
厚めの皮手袋をして、手に乗せて記念写真を撮る。ラクダ

70/70
ラクダを遊牧していた。
モンゴルではモンゴル高原を中心にラクダがいる。
ここのラクダは背中のコブが2つある、フタコブラクダ。
コブが1つのヒトコブラクダは中東から北アフリカにおり、フタコブラクダに比べて圧倒的に生息数が多い。